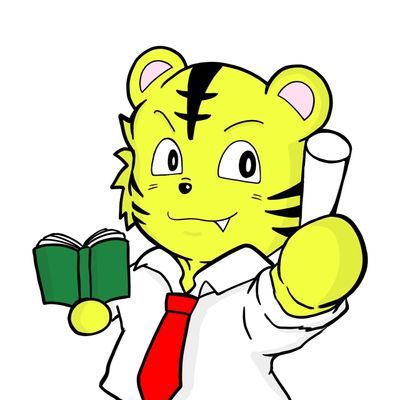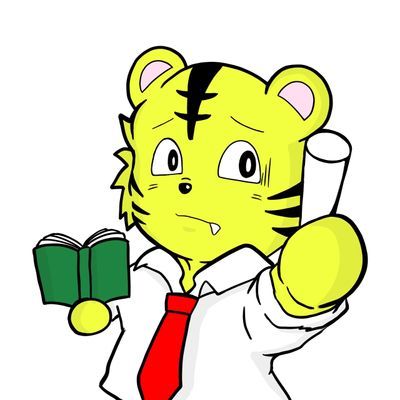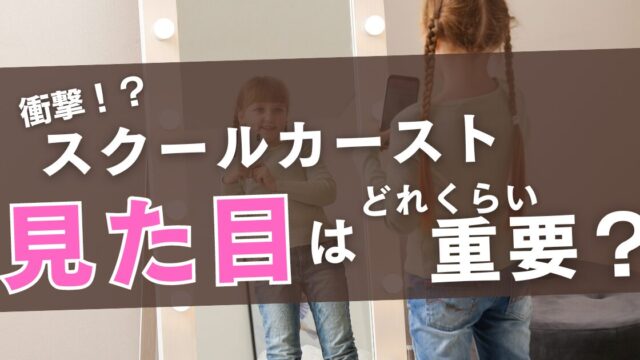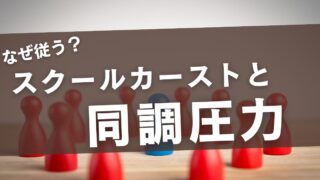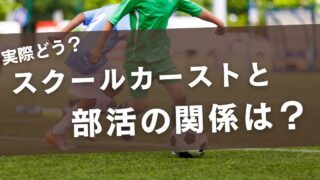スクールカーストっていつからある言葉なの?
「スクールカースト」は比較的最近できた言葉だよ!
「スクールカースト」という言葉が一体いつからできたのか気になりますよね。
いつの間にか使われ出して浸透してしまったためか、いつからある言葉なのかいまいち理解されていません。
「スクールカースト」という言葉は2007年にインターネットで使われ始めました。
この記事では、「スクールカースト」の由来やなぜ広まったかについて解説しています。
スクールカーストとは

スクールカーストとは、学校で見られる上下関係の階層(カースト)構造を示しています。
小学校の高学年から中学・高校で発生し、「1軍・2軍・3軍」「A・B・C」などと呼ばれるグループに分断される現象を指します。
人気度やコミュニケーション能力などが要因となった上位グループと中位・下位グループで構成されていることがほとんどです。
では、スクールカーストはいつから使われ始めた言葉なのでしょうか。
スクールカーストはいつから使われ始めるのか?
ここからはスクールカーストがいつから使われ出したのかを解説しています。
なお、解説には以下の2つの著書を参考にしています。
- 鈴木翔『教室内カースト』
- 堀裕嗣『スクールカーストの正体』
スクールカーストが登場したのはインターネット

スクールカーストが初めて登場したのは2007年のインターネットからです。
朝日出版の『AERA』という雑誌で「スクールカースト」という言葉を生み出した人物が、インターネット上に言葉を登録した、と語っています。
当時システムエンジニアのマサオさんが「スクールカースト」という言葉をインターネット上に登録し、説明文として以下の言葉を残しました。
主に中学・高校で発生する人気のヒエラルキー(階層性)。俗に「1軍、2軍、3軍」「イケメン、フツメン、キモメン(オタク)」「A、B、C」などと呼ばれるグループにクラスが分断され、グループ間交流がほとんど行われなくなる現象
鈴木翔『教室内カースト』
スクールカーストの意味を的確に捉えていると思われます。
その後、多くの書籍で引用されるようになりました。
誌面に初めて載ったのは書籍から
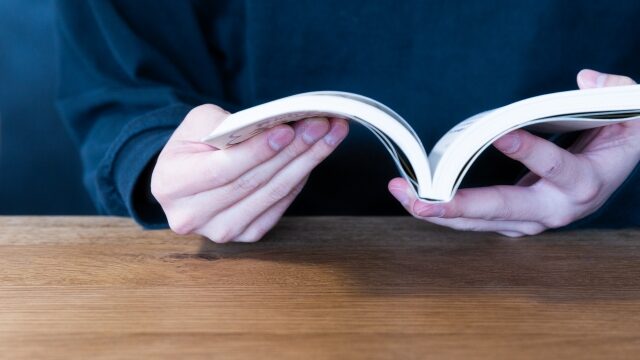
スクールカーストが誌面に初めて登場したのは、書籍からです。
森口朗さんの『いじめの構造』という2007年に出版された本の中で、初めて用いられました。
その著書の中では、スクールカーストは以下のように定義されています。
スクールカーストとは、クラス内のステイタスを表す言葉として、近年若者たちの間で定着しつつある言葉です。従来と異なるのは、ステイタスの決定要因が、人気やモテるか否かという点であることです。上位から「一軍・二軍・三軍」「A・B・C」などと呼ばれます。
森口朗『いじめの構造』
今となっては、ただの定義と思われるかもしれませんが、当時まだスクールカーストが理解されていなかった時に、人気やモテるという観点から生徒を観察し始めた功績は非常に大きいと言えます。
ん?初めて言葉を登録したのがネットの「マサオさん」なら、初めては「マサオさん」なんじゃないの?
確かにこの辺は複雑だね!整理してみる必要がありそうだね!
スクールカーストという言葉が用いられ出した順番を整理すると以下のようになります。
- マサオさんがインターネットに「スクールカースト」と登録
- 森口さんが著書で「スクールカースト」という言葉を使用
- 雑誌『AERA』のインタビューでマサオさんがスクールカーストという言葉を登録したことが判明
つまり、作ったのはマサオさんだけど、メディアに初めて紙のメディアに載せたのは森口さんってことだね!
ここまで理解しておく必要はないと思うけどね!
スクールカーストが流行したのはドラマの影響

スクールカーストはドラマの影響で、一般的な言葉として広められていきます。
堀裕嗣さんは著書の『スクールカーストの正体』でスクールカーストの普及を以下のようにまとめています。
スクールカーストという語が普及し始めたのは2000年代の半ばのことだったように思う。なんだか霞みたいにどこからともなく立ち現れ、次第にネットで話題になり、いつしか生徒たちの間でも使われるようになって、幾人かの社会学系の論者が取り上げ始めて、米倉涼子のドラマ(35歳の高校生)で爆発的に認知された。
堀裕嗣『スクールカーストの正体』
「35歳の高校生」というドラマは腕力やスポーツなど単純な指標でスクールカーストができることを伝えているという弱点があります。
しかし、学業とは異なる指標でクラス間の序列が決まっていることを描いたドラマとしては、スクールカーストを世に広めたと言えるのかもしれません。
その後、「俺、2軍だから!」や「私、1軍とだけ話したい」などを私も生徒から聞くようになりました。
生徒が「冗談」か「本気」のどちらで使っているのかわからず、不気味な感覚に陥ったのを覚えています。
数々のメディアに取り上げられるようになる

今では「スクールカースト」は生徒だけではなく、大人も使うようになりました。
さらに、メディアでも使われるようになっていきました。
スクールカーストを描いた本には以下のようなものがあります。
- 底辺女子高生
- 桐島、部活辞めるってよ
- 鼻とみつばち
- 女子高生Girls-High
- 12人の悩める中学生
- 大空のきず
- 野ブタ。をプロデュース
- ある日突然ハブられた
- スクールカースト最下位な僕らのありふれた日常
- スクールカースト殺人事件
こんなにもスクールカーストが描かれた本があるんだ!
直接、スクールカーストという言葉は出てこなくても、明らかに意識している作品も含まれているよ!
最近では、『進撃のスクールカースト』という大人気漫画『進撃の巨人』のパロディ作品も描かれているようですね。
急に流行り出したのは現代特有の理由が・・・

このサイトの読書の中には、スクールカーストが「2007年」から用いられたと聞いて、以下のように疑問をもたれた人もいるのではないでしょうか。
意外と最近なんだ⁉️もっと前からありそうだけど。
スクールカーストという現象自体はありましたが、言葉自体が生まれたのは2007年です。
つまり、クラス内で序列が決まっていく現象はずっと前からあったと言っていいでしょう。
しかし、私はそれでもスクールカーストは最近の学校に特有の現象だと考えています。
参考:【現在は?】スクールカーストの現状はどのようになっているのか?
文部科学省は「生きる力」「学びに向かう人間性」などを重視しています。
さらに、昔よりも「勉強だけできても・・・」「人間性が伴っていないと!」という言葉が使われるようになっています。
昔であれば、「学業成績」の順番がそのままクラス内での序列と一定の関係がありました。
しかし、勉強が昔より重視されなくなり、それ以外の要素で順位づけをするのは現代特有の現象と呼べるでしょう。
参考:スクールカーストと勉強や学歴との関係は?【あまり関係ない!】
まとめ
まとめましょう。この記事では以下のことを解説しました。
- スクールカーストはネットで初めて使われた
- 誌面で初めて掲載されたのは書籍
- 様々なメディアを通じて、認知されていった
- 最近になって認知されてきたのは、現代特有の現象だからかもしれない
スクールカーストという言葉が生まれてきて、20年以上が経過しようとしています。
言葉は登録しても、誌面で出てきても、それだけで使われることはありません。
スクールカーストという言葉がこれほどまでに広まったのは、多くの人が学校で抱えていたモヤモヤが言葉になって現れたからではないでしょうか。
だからこそ、こんなにも「スクールカースト」という言葉は深く我々の生活にまで浸透する言葉になったのかもしれません。
このサイトでは、他にもスクールカーストに関する記事を公開しています。
ぜひ、他の記事もご覧ください。